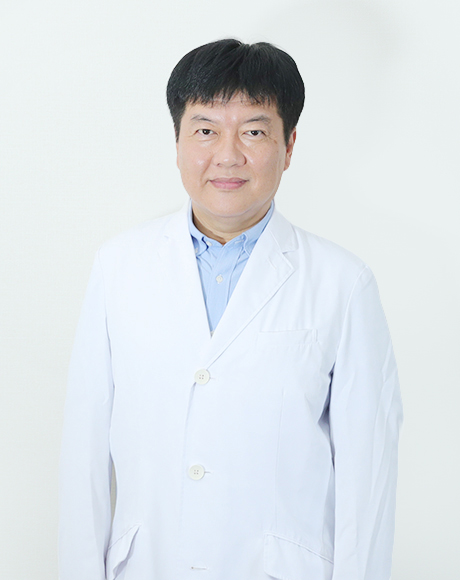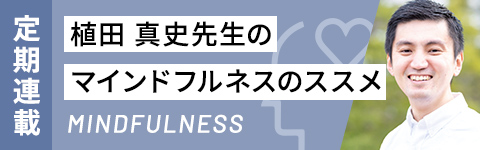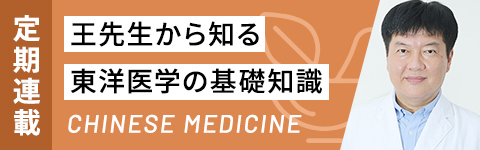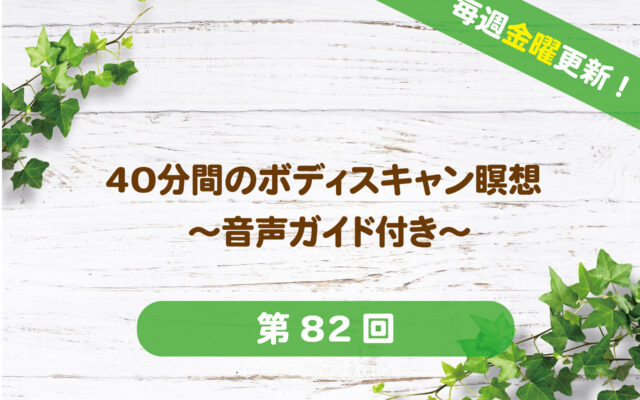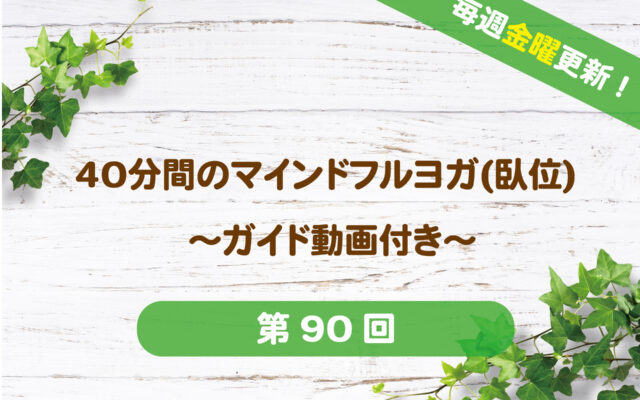はじめに読むコラム
こちらの記事は東洋医学の「基礎」となるコラムです、より理解していただくために、まず、はじめにご覧ください。
日本漢方と中国中医学の比較表

|
対比表 |
||
|
区 分 |
日本漢方 |
中国中医学 |
|
概念 |
「漢方」は日本の伝統医学とされるが、ほぼ「漢方薬」のみを指す。日本の「東洋医学」は主に「漢方」と「鍼灸」を合わせたものを指す。 |
「中医学」は「中国伝統医学」を指す。中薬、鍼灸、推拿按摩、気功太極拳などの治療法も含まれる。 |
|
医学教育 システム |
ほとんどの医科大学医学部に漢方医学教育は導入されているものの、履修する単位数が少ない。このため、漢方医学の知識は大学卒業後、自分の興味や診療ニーズに応じて独学あるいは勉強会などに参加することで習得することがほとんどである。 |
中医薬大学及び大学院が設置されており、大学生・大学院生向けの包括的な中医学教育システムが構築されている。 |
|
医師資格 (免許) |
大学医学部(西洋医学)の卒業生のみが医師の免許を取得できる。「中医学」や「漢方」のような医師(中医師)免許制度はない。このため、日本で医療用漢方を処方できる者は西洋医学の医師免許を取った者に限られている。 |
中医薬大学を卒業し、国家の中医師免許試験を受け合格すれば中医師免許を取得できる。中医師は漢方と西洋薬の両方を処方できる。教育訓練を受ければ手術も可能。 |
|
処方および 薬剤 |
2種類に分けられる。 医師の処方が必要で国民健康保険が適用される医療用漢方は、148種の方剤と160種の生薬に限られる。 一般用漢方は297種の方剤と350種類の生薬あり、非処方薬(OTC)として薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されているものの健康保険は適用されない。 |
最新の『簡明中成薬辞典』には、臨床で常用される3,474種の複合処方及び5,800 種の生薬製剤が収録されている。そのうちに700種類以上の生薬が使用される。 |
|
医学理論 出典 |
基本的には古典、主に『傷寒論・金匱要略』に掲載された処方・用法に従って漢方薬が処方されており、弁証論治は重視されていない。 |
『黄帝内経』に基づき、陰陽・五行・臓腑・気血津液・経絡などの基礎理論と「弁証論治」診断法をともに重視しており、患者の具体的な状況に適した漢方薬を作り出す。 臨床処方治療学の出典『傷寒論・金匱要略』など。薬物学の出典『神農本草経』など。 |
|
薬および 使い方 |
医療用漢方薬は基本的には顆粒剤であり、古来の処方が多く、近現代に研究開発された新しい漢方はない。 医療現場では漢方薬を単に薬として使用する傾向にあり、漢方医学の知識や理解がなくとも医師は「漢方マニュアル」により、西洋薬と同じように漢方薬を処方することができる。 もちろん、中医学の考え方をもとに漢方薬を処方する医師もいる。 |
中医学理論に基づいて、古代から現代まで多くの処方が生み出され、時代の進歩に応じて絶えず新しい中成薬(製剤化した中薬)が開発されている。 薬局店頭に医療健康保険用の基本薬物以外にも数え切れないほど大量のOTC中成薬もある。 薬剤の型も丸剤、錠剤、顆粒剤、糖漿剤、注射剤など様々な種類がある。 「弁証論治」「因人制宜」などの理論を重視する中医学の使い方は知識と経験が必要で、技量がないと実際の応用において難しいと感じられる。 |
|
診断方法 |
病名、あるいは主な症状に応じて漢方薬を処方することは多い。腹診を重視。 |
「弁証論治」として、「望・聞・問・切」の四診により得た患者の情報を総合的に判断して「証」を決めて治療方針と処方を決める。 |
|
虚実判定 |
体力充実度(体質や症状)で判定 |
正気・邪気(病態)の相互関係で判定 |
|
治療特徴 |
方証相対(証と処方と一体) |
弁証論治(病因病機) |
|
長所 |
主にエキス剤を使用 |
主に生薬加減(テーラーメード) |
|
短所 |
急性疾患にエキス剤の効能が弱い |
煎じ薬は時間要す、飲みにくい |
|
西洋医学との結合 |
漢方を処方できる人はすべて西洋医学専門の医師であるため、基本的には西洋医学の視点から患者の病気を診ることが主流となっている。 |
中医師は大学在学中に中医学のみならず、西洋医学も履修する。西洋医師であっても中医学を学ぶことが推奨されている。 一部の大学では一つの教育システムとして、中西医結合医学学部も設置されている。 |
|
医療施設 |
漢方の医院・診療所・クリニック、一部の総合病院や大学附属病院において、漢方外来や漢方内科などの診察室が設置されている。 |
各地方の公私立の中医専門病院(外来と入院)及び西洋医学中心の総合病院の中に中医学の診療室(外来)、中西医結合医学の専門病院が設置されている。 |
参考文献:
- 関口善太著.〈イラスト図解〉東洋医学のしくみ.日本実業出版社,2003
- 清水宏幸.新しい医療革命―西洋医学と中国医学の結合.集英社,2004
- 安井廣迪著.医学生のための漢方医学【基礎編】.東洋学術出版社,2008
- 栗原 毅/中山貴弘/陳 志清/菅沼 栄/楊 暁波.漢方・中医学がわかる本.宝島社,2016
- 陳 志清.中医学と日本漢方の違い.『和華』第26号,2020