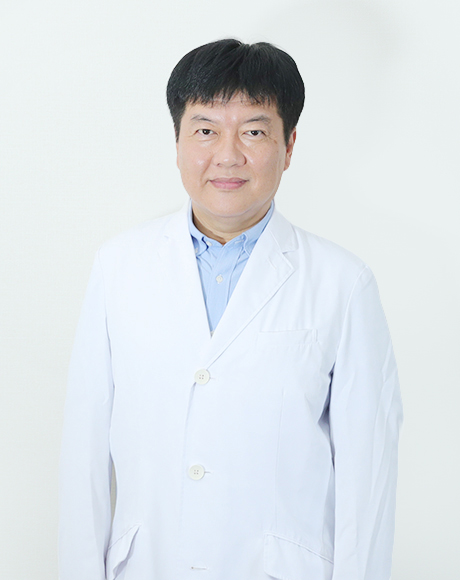はじめに読むコラム
こちらの記事は東洋医学の「基礎」となるコラムです、より理解していただくために、まず、はじめにご覧ください。

由来と特徴
マッサージはヨーロッパで生まれた手技療法で、元来、医療行為として行われ、原則として手で直接皮膚に触れて施術するものです。
多くの場合、衣服の上からではなく、直接、皮膚を「なでる」「さする」といった手技をオイルなどを手につけて行います。その手順は按摩とは逆に基本的に四肢の先端など体の末梢部から、心臓(体の中心)に向かって行います。
静脈の働きを助け、血液とリンバ液の巡りを促し、それらの滞りを改善します。また、緊張をほぐす効果もあり、心身のリラクゼーションを導くとともに、経絡の流れに沿った指圧や按摩などと併せて行うことで、治療の相乗効果も見込めます。
日本式マッサージ
日本には明治20年代に西洋医学療法の1つとしてフランス式マッサージがもたらされ、これに按摩の技術が取り入れられたことで、日本独自のマッサージが誕生しました。
マッサージは本来、東洋医学の範疇には属しませんが、東洋医学の考えをとり入れた治療院では様々な手技を複合的に組み合わせることで、より高い効果が得られることから、経絡や経穴を利用した手技療法を補う目的で、マッサージを用いることが多いようです。西洋医学的な考え方による筋肉や関節、腱、皮膚へのアプローチを加えることで、総合的な治療ができるようになりました。
また、マッサージは皮膚に直接触れますので触診の意味もあり、患者の身体の状態がよりわかりやすくなるという利点もあります。マッサージの手法を用いることで、経絡の流れなどを診断し、鍼灸やそのほかの手技療法などで不足する治療効果を補う場合もあります。
多方面的効果
マッサージでは、手のひらや指などで皮膚に直接刺激を与えるため、その潤滑剤としてオイルを使用します。肌にオイルなどを塗ることで手のすべりがよくなり、よりスムーズな手技により血液やリンパの循環を改善効果が高まるのです。
基本となるマッサージの手技にはさまざまな種類があり、筋肉のこわばりをほぐして血流を改善する、神経活動を鎮静させるなど、目的に応じて手技を組み合わせながら行います。
手技は以下の6つに分類されています。
- 軽くなでさする軽擦法
- 筋肉をもみほぐしていく揉捏法
- やや強めになでさする強擦法
- 手指で叩く叩打法
- 手のひらや指で押していく圧迫法
- 細かく振動を与える振せん法
痛みやこりなどの症状改善、皮膚の保湿といった美容効果がよく知られていますが、その心地よい刺激によって心身ともにゆったりと緊張を和らげるなどのリラックス効果があります。そのため、精神面でのリラクゼーション目的で行われることも多いようです。
参考文献
- 関口善太著.〈イラスト図解〉東洋医学のしくみ.日本実業出版社,2003
- 安井廣迪著.医学生のための漢方医学【基礎編】.東洋学術出版社,2008
- 平馬直樹・浅川要・辰巳洋著.オールカラー版 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書.株式会社ナツメ社,2014
- 仙頭正四郎著.最新 カラー図解 東洋医学 基本としくみ.株式会社西東社,2019