
ここ35年程の間、人類はすさまじい勢いでコミュニケーションテクノロジーを創造してきました(初期大型携帯電話→ガラケー→iモード→インターネット→スマートフォン→AI等々) テクノロジーは発達しましたが、この間に人間の能力(生身の人間の能力)が発達したか?進化したか?(テレパシーみたいなことができるようになったか?)便利になったのだけど、人間のコミュニケーション能力が高くなったかというと、けっしてそうではないように感じられます。むしろ便利なった分、脆く・弱く・貧弱に・脆弱になったのかもしれません。(一般的なビジネスや社会生活においてAIの利便性は多大なものですが・・・)
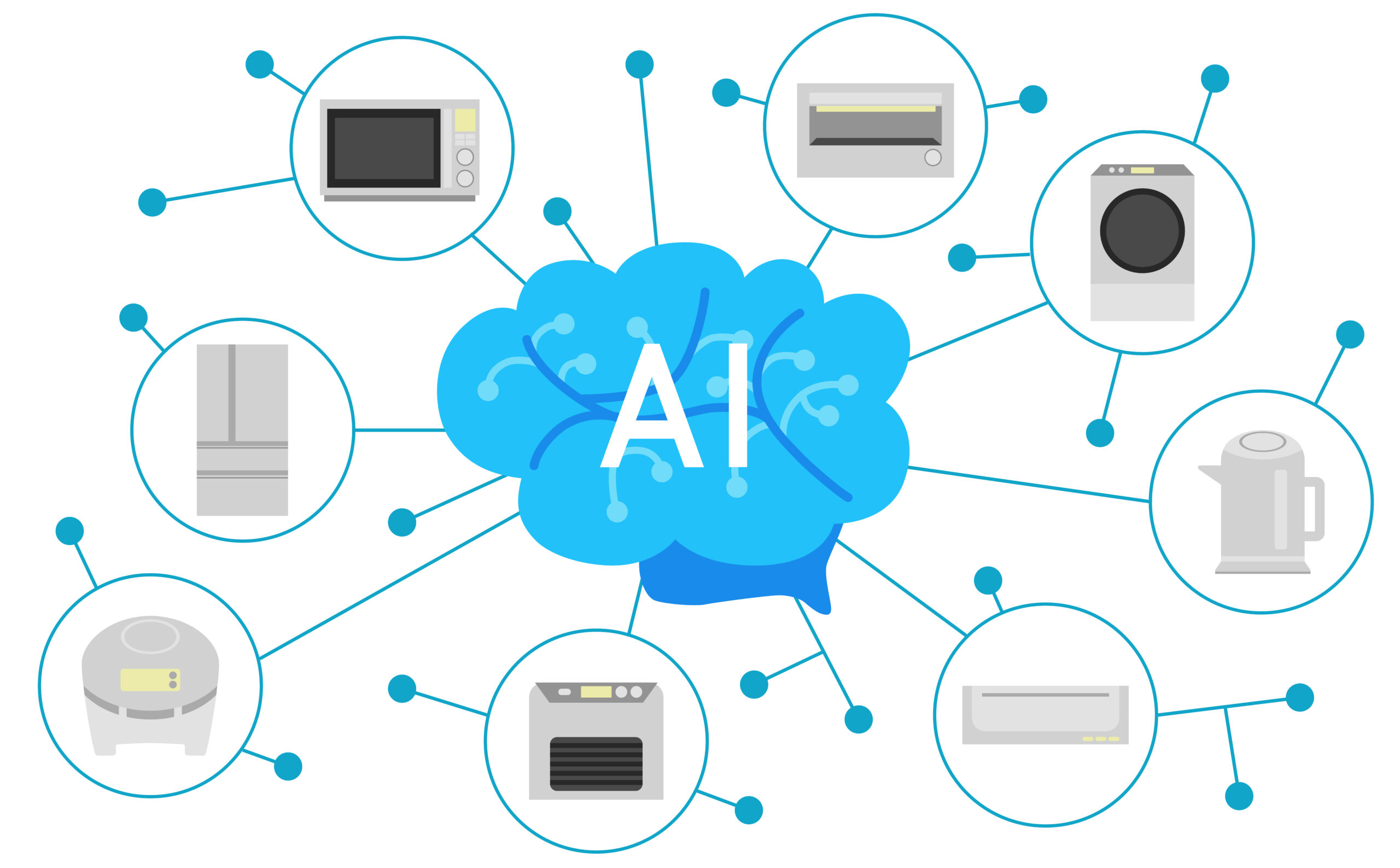
養老孟司さんが、ある講演の中で「人間は楽をすると弱くなる」と言われていました。この考え方の本質は過度な快適さや便利さを追求する現代社会に対して、楽な状況が続くと人は本来持っているはずの力を失ってしまう、という考えがあるのではないでしょうか?
急激に発達したインフォメーションテクノロジーにおいて、現代人が自身の体や自然とのつながりを忘れ、便利さに依存しすぎている現状があり、例えば、過保護な環境で育つと、自分で考える力や困難を乗り越える力が育ちにくくなりますし、常に快適な環境にいると、暑さや寒さ、空腹といった体のサインに鈍感になり、変化に対応する力が衰えてしまいます。
「楽をする」
「楽をする」とは、単に肉体的な楽さだけでなく、精神的な楽さ、つまり、自分で考えたり、努力したりすること、また他者との複雑なコミュニケーションプロセスを避けることも含みます。そのような状態が続くと、人は主体性を失い、外部からの刺激やITツールに依存するようになり、結果として「弱く」なってしまう。つまり現代人は我々の本来持っていたコミュニケーション能力が下手すれば退化しているかもしれません。
医療や介護・福祉サービスに関わるスタッフは、特に患者・その家族・医療や介護の施設を利用されている方々とのコミュニケーションにおいては、いつもタブレット・スマホ等でやり取りするという訳にはいきません。あくまでも対面の双方向のコミュニケーションが基本です。そこにはお互いの気質・価値観・信念体系・感情・行動が複雑に絡み合い、相互の関係性を築いていくプロセスとストーリーが生まれるわけです。
また、多職種が協働して働く臨床現場では、とりわけ“チームワークとコミュニケーション能力”が期待されていることは言うまでもありません。
これから、この部屋(人とチームを学ぶ部屋)では人やチームがどのようにふるまう事(行動すること)がより良い成果(医療や介護・福祉の現場で)を生む可能性があるのかを探求していきたいと思います。
独り言

私の趣味は磯釣りです。磯釣りと言っても色々と種類があるのですが、私の領域は夜釣りです。長崎県の平戸や五島列島の磯(海に浮かぶ岩場)に行って“夜釣りを一人で楽しむ”わけです。そう書いてしまうと「なんだ、ただの釣り好きのおじさんか!」と思われるでしょうがじつは、釣行の目的はいわゆる釣果を上げるためだけではなく、“真っ暗な闇の中たった一人で五感をフルに使って生きること”が目的にあります。いわゆるサバイバル体験です。こういった環境に身体を置くと、いかに五感を使うことが重要かと思わされます。
私の場合は積極的に五感を活用せざるを得ない状況を創っているのですが、植田真史先生のマインドフルネス瞑想では、私の様な究極の環境ではなく、ごく普通の自然環境の中(森の中の木々の揺れや小川のせせらぎ、鳥のさえずりなどの自然環境の中)で五感に意識が向けられると言われています。
「自然の中でマインドフルネス瞑想を実践する際には、五感に意識を向けて環境を感じとることが大切です。例えば、木々の葉が風に揺れる音や足元の土の感触に注意を向けることで、今この瞬間に集中しやすくなります(植田真史先生 自然の中でのマインドフルネス瞑想)」
皆さん五感をフルに活用して生きる場面・生活する場面はありますか?












